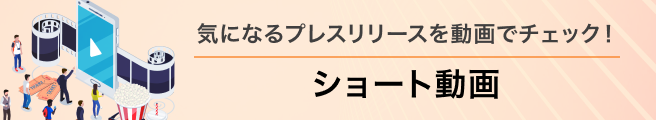【川端祐一郎】アキレス腱を射られた現代社会――中華未来主義と新型コロナ騒動

From 川端 祐一郎(京都大学大学院助教)
表現者クライテリオンの最新号が、発売されました。
https://the-criterion.jp/backnumber/90_202005/
今回の特集は「中華未来主義との対決」です。その趣旨は恐らく、中国に対する批判というよりも、未来主義批判であると捉えていただくほうが分かりやすいと思います。
欧米の左派の一部に、「加速主義」と呼ばれる、ポストモダンを拗らせたような矯激な思想を唱える人々が存在するようです。彼らは、「資本主義の弊害と闘う上で、現代の左翼運動にはラディカルさが足りない」との問題意識を持っていて、むしろ資本主義の土俵の上でテクノロジーの水準を極限まで高め、社会や文化のあり方を根本的に変革してしまうことで、いま我々を悩ませている不正義や不満を解消することができるという期待を持っているらしい。
例えばニック・ランドという哲学者は、人種差別を根絶するためには啓蒙活動や法制度に頼るのではなく、人間の遺伝子操作技術を普及させることで、人種という概念そのものを無意味にしてしまえばよいのだと主張しています。さすがに極論なので直接の支持者が多いわけではないでしょうが、これを少し薄めたような技術未来主義は、すでに現代世界を覆っているとも言えるでしょう。加速主義のイデオローグの一人が、ペイパルの共同創業者で敏腕ベンチャー投資家のピーター・ティール氏であることからも、この思想が単なる「カルト」で済まされるものではないことが分かります。
加速主義は政治思想の一種であり、単なる技術礼賛には留まりません。加速主義者たちは例えば、民主主義のように人間臭く非効率なルールは捨ててしまって、少数の強力なリーダーが技術を駆使して人民を合理的に管理したほうがよいのだ、という秩序観を持っているようです。そして、現時点でそれを最も色濃く体現しているのは中国政府であり、だから加速主義者たちは、中国型の国家運営が世界標準になることを望んでもいるらしい。
歴史的に培われた国民文化ではなく、技術的な管理によって社会秩序を形成する。
中間集団による自治ではなく、中央集権的なトップダウンの意思決定が強い力を持つ。
自由や平等のような啓蒙的理念ではなく、経済成長や安全保障のような現実的利益を重視する。
そういう加速主義的な統治のあり方に対する期待が、日本を含む旧西側諸国においてすら、高まる兆候が見え始めています。新型コロナの騒動においても、人類は自然の猛威に対する畏れの感覚を取り戻すというよりは、むしろテクノロジー信仰とトップダウン的な管理主義を加速しつつあるように見えますね。
原因はもちろん、従来型の自由民主主義がうまく機能しているとは言えなくなってきたからです。加速主義者が言うような技術的管理の全面化は、我々を地獄に導くとしか思えないのですが、今の先進国社会においては、そういう警戒感が希薄化してきているかも知れません。だから重要なのは、中国との戦いであるというよりも、我々自身との戦いなのです。
今回の特集ではレギュラー執筆陣に加えて、『ニック・ランドと新反動主義』の著者であり、加速主義の思想を日本に紹介してこられた木澤佐登志氏、中央アジア史やユーラシア史の専門家で、昨年は雑誌『世界』(2019年4月号)で「権威主義」の台頭について示唆に富む状況分析を書いておられた宇山智彦氏、そして中国思想の専門家で、最近は中国の現代思想をリベラル派の立場から包括的に論評した『新全体主義の思想史』(著者は張博樹)を翻訳された石井知章氏にご寄稿いただいています。座談会では、「中国化」というキーワードで日本や世界の情勢分析をしてこられた與那覇潤氏にご登場いただきました。
宇山氏は、今広がっているのは「中華未来主義」ではなく「中華現在主義」であると指摘しています。旧西側諸国においても、あるいは一帯一路戦略などを通じて中国の影響力が増しているとされる中央アジア諸国においても、中国的な統治スタイルが今後の世界のモデルになると本気で信じている人は、現実には少数である。むしろ我々は、中国の「現在」の爆発的膨張に翻弄されていて、「自由民主主義」という旧来の理念の魅力も色褪せているために、未来のビジョンを描くことができずに右往左往していると言うべきだろうと。なるほど、確かにその通りでしょう。
特集座談会でも申し上げましたが、我々現代人は、教条的な理念としての民主主義や資本主義については飽きるほど論じてきた一方で、具体的な生活感覚や民族感情に基づいて、そもそもどんな社会を生きたいのか、どんな歴史を紡ぎたいのかを言語化する努力を怠ってきたように思います。そのせいで、手持ちの理念が通用しない局面では、何を土台に「社会のあるべき姿」を語ればよいかが分からなくなってしまう。そして、中国の急速な台頭や、新型コロナウイルスの登場は、その弱点を鋭く突いているのです。
前回のメルマガで、コロナ騒動の背後にある「生命至上主義」の問題に触れましたが、私は「人々が死ぬことを恐れてばかりいて情けない」ということが言いたかったわけではありません。また、現在の活動自粛は過剰であり、経済対策は過少だと思うのですが、そういう政策判断の妥当性を論じたかったわけでもありません。私が気になっているのは、政策決定それ自体というよりも、社会活動の自粛を正当化する言葉があまりにも平板であることや、緊急事態宣言を求める国民の声に迷いの形跡が見当たらないことの不気味さについてです。
一例として、身近なことを考えてみましょう。たとえばマスクを着けて電車に乗る場合に、「人様にウイルスをうつしてはいけないからマスクを着ける」という人はいるでしょう。一方、「相手が悪人でなければうつしたくはないが、クソ野郎ならば何とかしてうつしてやりたい。しかし、にわかに善人と悪人を見分けるのは難しいし、悪人だけを狙ってうつすのも容易ではないから、とりあえずマスクを着けておこう」という方針もあり得ます。これらは、外形的には全く同じ行動に見えるものの、人間的な意味はかなり異なります。
私はこの2つなら、前者のような綺麗事よりは、後者のような行動原理を支持します。「人様」一般を等価なものとして扱うヒューマニズムはニヒリズムの温床となるからで、これは西部邁先生が繰り返し論じ続けたことでもあります。(もちろん、宗教的信念や医者としての使命感から「全ての人を等しく救うべし」と結論するなど、別の原理も様々にあり得ます。また、マスクとは関係ありませんが、戦場の軍人なら、相手がいかな人格者であれ戦わねばならないのでしょう。)
その上で、「どの程度の悪人が相手ならマスクを外すべきか」「俺は碌でもない人間だからうつされても致し方ないのではないか」というようなことについて、冗談もまじえながら会話を重ねていくことで、我々の人間観は奥行きを持ち、社会観が広がりを獲得するのだと思います。もちろん、どれだけ議論を続けたところで、個々の具体的局面において、マスクを付けるかどうかや活動を自粛すべきかどうかについて、決定的な結論を得るのは難しいでしょう。しかし、何の迷いもなく「命が大事なんだから自粛しましょう」とやるのに比べれば、ましであると私は思うわけです。
社会に自粛を求める場合も、それなりの言葉を尽くす必要があります。新型コロナでは致死率が低すぎるので、ここでは仮に、流行っているのがエボラ出血熱だとしましょう。感染すればまず間違いなく死ぬわけですから、たとえば甲子園の野球大会も中止せざるを得なくなります。しかしその場合でも、県予選を勝ち抜いた高校球児の一部からは、「俺たちは死んでもいいから試合をしたいんだ」という声が挙がるでしょう。
そのとき、例えば私みたいな人間が「危険だからやめなさい」と怒鳴っても、納得するわけがありません。しかし戦中派の元プロ野球選手のような人物が出てきて、「私も80年前に、戦争で大会が開かれず、君たちと同じように悔しい思いをした。しかし自分の野球人生を振り返ると、それ以上に悔しいことも山ほどあった。後になればどうということはないし、それも野球人としての糧になるから、今は練習に励みなさい」というようなことを語れば、納得してくれるかも知れません。
要するに、政策や行動というのは、結果的に同じ形を取るにしても、それが背負っている言葉によって価値が大きく変わるのです。ところが、今の日本に溢れている言葉といえば、命は何よりも重いもので、しかもその重みはすべて等しいというヒューマニズムを前提とした綺麗事ばかりです。もちろん政策提案の最前線では、「悪人は救わなくてよい」というような差別的論理を語るのは難しいでしょうから、割り切った議論が行われるのも分かります。しかし私の観察するところ、その後背に広がるジャーナリズムの空間においても、あるいは日常の生活現場においても、官僚仕事のように硬直し切った綺麗事しか聞こえてこないのです。
(稀な例外として、医師でありジャーナリストでもある森田洋之氏のブログエントリには感銘を受けました → リンク1・リンク2)
死ぬのが怖いなら怖いで、伝染病で死ぬことの無念や悲哀について語ることが色々あるはずだし、怖くないなら怖くないで、冒険的行為の魅力ぐらいは語ってもいいはずです。40万人死ぬという大げさな予想が仮に正確であったとして(あるいは流行っているのが新型コロナより遥かに強毒なウイルスであったとして)、「それでもこの活動は自粛したくないのだ」と言いたい人もいるはずです。
しかし今は、誰もが優等生を演じることを強いられている。強いられるばかりか、自ら進んで「俺のほうが危機感がある」というような競争に明け暮れる人も少なくない。そして恐ろしく多弁である割には、その論理を突き詰めると、「命が大事」程度の恐ろしく平板な道徳原理しか持っていないことが多いのです。政策決定は全ての人を満足させることができず、優等生側に倒れがちであるのは致し方ないにしても、少なくとも迷いぐらいはあって然るべきで、その迷いを言語化する努力の中で人の価値観は成熟するのです。
私は、政策や行動の背後にある言葉の貧困こそが、現代日本のアキレス腱になると思っています。どんな社会が生きるに値するのか、どんな人生に敬意を払うべきであるのかという、曖昧で複雑にしか語りようのない問題について言葉を尽くしておかないと、状況が少し変わるたびに狼狽しなければならなくなる。その意味で、「中華現在主義」も「新型コロナ騒動」も、問題の根は同じだと見ておくべきでしょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガのバックナンバーはこちらで閲覧頂けます。
https://the-criterion.jp/category/mail-magazine/
雑誌『表現者クライテリオン』の定期購読はこちらから。
https://the-criterion.jp/subscription/
Twitter公式アカウントはこちらです。フォローお願いします。
https://twitter.com/h_criterion
その他『表現者クライテリオン』関連の情報は、下記サイトにて。
https://the-criterion.jp
ご感想&質問&お問合せ(『表現者クライテリオン』編集部)
info@the-criterion.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━