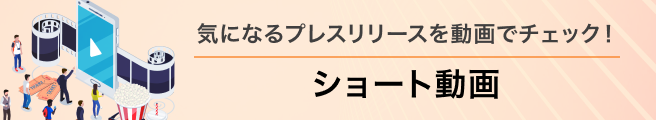卵巣がんに対する分子標的薬「ベバシズマブ」の効果を解析 投与終了後に悪化リスクが高まることを確認、最適な投与法を提案

近畿大学医学部(大阪府大阪狭山市)産科婦人科学教室主任教授 松村謙臣と、京都大学大学院医学研究科(京都府京都市)婦人科学産科学教室特定助教 高松士朗を中心とする研究グループは、卵巣がんの臨床試験データから、血管新生阻害剤※1「ベバシズマブ(商品名:アバスチン)」の効果が投与期間等によってどのように変化するかを解析しました。その結果、ベバシズマブの投与が終了すると悪化リスクが高まる「リバウンド効果」が見られることを確認し、それを元にベバシズマブの最適な投与方法を提案しました。
本件に関する論文が、令和5年(2023年)8月3日(木)AM1:00(日本時間)に、臨床医学領域の国際的な科学雑誌"JAMA Network Open(ジャマ ネットワーク オープン)"にオンライン掲載されました。
【本件のポイント】
●卵巣がん治療に用いられる分子標的薬※2 ベバシズマブの、投与期間と効果の関連性を解析
●卵巣がん初回治療時において、ベバシズマブの投与終了後に悪化リスクが高まる「リバウンド効果」を確認
●ベバシズマブの効果が最も高い時期を明らかにすることで、最適な投与方法を提案
【本件の背景】
ベバシズマブは、血管の新生を阻害し、がん細胞の成長に必要な栄養の供給を妨げて死滅させる分子標的薬で、卵巣がんの治療に最も多く使用されています。平成23年(2011年)の先行研究において、化学療法との併用後に維持療法としても用いることで、無増悪生存期間※3(PFS)が延長し、増悪リスクも減少したことから、日本を含む世界各国で薬事承認されました。しかし、ベバシズマブは得られる効果に対して薬剤費が高く、高血圧、タンパク尿、腸に穴があく腸穿孔などの副作用も認められ、さらに全生存期間※4(OS)は延長させる効果がないと報告されたことから、卵巣がんの標準治療としてベバシズマブを用いるべきかについては、さまざまな意見があります。そこで、本研究グループは、ベバシズマブをどのような卵巣がん症例に用いるべきかを明らかにするため、臨床試験のデータを詳細に再解析しました。
【本件の内容】
研究グループは、公開されている卵巣がんの臨床試験データを用いて解析を行い、ベバシズマブを投与し始めた最初の12カ月間はベバシズマブ投与群の方が増悪リスクは低いものの、投与を中止した12カ月以降は、ベバシズマブ投与群の方がむしろ増悪リスクが高くなる「リバウンド効果」が認められることを見出しました。
また、生存曲線※5 を画像的に解析して経時的な増悪リスクの変化を調べる方法を開発し、手術時に残った腫瘍や、特定の遺伝子変異、化学療法感受性の有無によらず、ベバシズマブ投与終了後に増悪リスクが高くなるリバウンド効果が一貫して観察されることを明らかにしました。
今回の結果は、卵巣がんの初回治療におけるベバシズマブの効果は限定的で、ベバシズマブを継続的に投与する再発時の方がベバシズマブの有用性が高いことを示しています。なお、近年は卵巣がんに対して、ベバシズマブ以外の分子標的薬の開発が進んでおり、ベバシズマブを他の分子標的薬と併用した場合の効果については、今後さらなる検討が必要です。
【論文概要】
掲載誌:JAMA Network Open(インパクトファクター:13.8 @ 2022-2023)
論文名:
Time-Dependent Changes in Risk of Progression During Use of Bevacizumab for Ovarian Cancer
(卵巣がんに対するベバシズマブ使用中の増悪リスクの経時的変化)
研究者:高松士朗1、中井英勝2、山口建1、濱西潤三1、万代昌紀1、松村謙臣2※ ※ 責任著者
所属 :1 京都大学大学院医学研究科婦人科学産科学教室、2 近畿大学医学部産科婦人科学教室
【研究詳細】
通常、臨床試験における2群間の生存曲線の比較は、2群の間の増悪リスクや死亡リスクの比が経時的に常に一定である(比例ハザード性が成立している)という仮定のもとに、そのリスク比(ハザード比)が数値化され、その結果、「死亡リスクが30%減少した」などと評価されます。抗がん剤などの殺細胞性化学療法剤※6 の効果を調べる臨床試験では、多くの場合この解析方法が有用ですが、分子標的薬の効果を調べる臨床試験の場合は、増悪や死亡を抑制する効果が経時的に変化しており、比例ハザード性が成立しないケースがあります。そのような場合に比例ハザードモデルによる解析を行うと、臨床試験の結果に関する解釈に混乱が生じてしまいます。一方、生存曲線の下の面積を比較する、制限付き平均生存期間(RMST)解析は、比例ハザード性が成立していない場合の解析手法として有用と考えられていますが、まだ広く用いられていません。
研究グループは、ベバシズマブを用いた7件の無作為化第III相試験(ICON7、GOG-0218、BOOST、GOG-0213、OCEANS、AURERIA、MITO16B)の公開データを用いて、ベバシズマブの効果の時間依存的変化に着目して再解析することで、ベバシズマブの最適な使用法を探索しました。ICON7試験は、卵巣がんの初回治療時においてベバシズマブを化学療法と併用で5-6サイクル、その後維持療法として3週間ごとに12サイクル(合計12カ月間)投与した際の有用性を検証した臨床試験であり、合計1528症例のデータが登録されています。研究グループは、そのうち745症例において、症例ごとの生存期間のデータ、および腫瘍の遺伝子発現プロファイルを入手し、このデータをICON7-Aコホートと名付けました。これを解析し、ベバシズマブ投与群と非投与群の無増悪生存期間の生存曲線を比較することで、比例ハザード性が成立していないことを示しました。そこで、RMST解析を行い、投与を開始した最初の12カ月間は投与群の方が増悪リスクは低いものの、ベバシズマブ投与を中止する12カ月以降は投与群の方が非投与群に比して増悪リスクが高くなるリバウンド効果が認められることを見出しました。このリバウンド効果は、進行卵巣がんの大多数を占める組織型の漿液性がん※7 ではDNA相同組み換え修復異常の有無によらず認められますが、非漿液性がんでは認められませんでした。
また研究グループは、生存曲線を画像的に解析する手法を開発しました。この手法を用いると、症例ごとの生存期間のデータを入手できない臨床試験であっても、論文で公開されている情報から経時的な増悪リスクの変化を調べることができます。解析に用いたデータのうちGOG-0218試験は、ICON7試験と同様に、卵巣がんの初回治療において、ベバシズマブを化学療法と併用で5サイクル投与した後、維持療法で16サイクル(合計15カ月)投与した際の有用性を検証した臨床試験です。研究グループは、生存曲線の解析によって、ICON7およびGOG-0218のコホート全体に加え、手術時に残った腫瘍、DNA相同組み換え修復経路の遺伝子変異、化学療法感受性の有無で層別化したサブグループにおいて、ベバシズマブ投与終了後の時期には、投与群の方が増悪リスクが高くなるリバウンド効果が一貫して観察されることを示しました。そして、ベバシズマブの投与期間を30カ月まで延長させた場合の効果を調べたBOOST試験でも、30カ月を超えてから投与群の増悪リスクが増加するリバウンド効果があることを示しました。一方、これとは対照的に、再発した卵巣がんを対象として、ベバシズマブを中止せずにがんが増悪するまで投与した際の有用性を検証した臨床試験(GOG-0213、OCEANS、AURERIAおよびMITO16B)では、投与群のリバウンド効果は観察されませんでした。
これまでの臨床試験によって、卵巣がん初回治療時におけるベバシズマブは15カ月まで投与するのが標準的な方法となっています。今回、研究グループは、卵巣がん初回治療時において、ベバシズマブは投与開始後約1年間はがんの増悪を抑制しますが、その後は投与中止によりリバウンド効果が認められることを示しました。今回の結果は、卵巣がんの初回治療におけるベバシズマブの効果は限定的で、ベバシズマブを継続的に投与する再発時の方がベバシズマブの有用性が高いことを示しています。
なお、最近は卵巣がんの化学療法後に、再発を防ぐ目的でPARP阻害剤※8 の維持療法が広く行われるようになってきました。ベバシズマブをPARP阻害剤と併用した場合の効果については、今後のさらなる検討が必要です。
【研究代表者コメント】
松村謙臣(まつむらのりおみ)
所属 :近畿大学医学部産科婦人科学教室
職位 :主任教授
学位 :博士(医学)
コメント:最近、婦人科がんに対する薬物療法は分子標的薬の導入によって大きく変わってきました。ベバシズマブは分子標的薬の一種であり、がん細胞に栄養を供給する血管の新生を阻害することでがんの増大を防ぎますが、がん細胞を根絶するわけではありません。このように、薬剤の作用メカニズムを十分に理解し、その有用性と限界を認識することが、それぞれの患者さんにとって最適な薬物療法を選択することにつながります。
【用語解説】
※1 血管新生阻害剤:血管新生を抑えることでがんの増殖を抑える薬。抗VEGF-A抗体であるベバシズマブは代表的な血管新生阻害剤である。
※2 分子標的薬:正常の細胞も障害を受ける従来の抗がん剤とは異なり、がん細胞の増殖などに関わる特定の分子のみを狙い撃ちして、その働きを抑える薬。
※3 無増悪生存期間:抗がん剤の治療成績の評価に一般的に用いられる指標であり、試験登録日もしくは治療開始日から増悪もしくは死亡が確認されるまでの期間と定義される。中央値を代表値として表現することが多い。
※4 全生存期間:患者の登録から死亡までの期間。中央値を代表値として表現することが多い。
※5 生存曲線:特定の集団が生存し続ける確率を時間の経過とともにグラフ化したもの。
※6 殺細胞性化学療法剤:いわゆる「抗がん剤」として以前から用いられてきた薬剤の総称。増殖する細胞を標的とし、腫瘍細胞の細胞死をもたらす。一般的に、白血球減少、嘔気、脱毛などの副作用が認められる。
※7 漿液性がん:卵巣がんのなかでもっとも多い組織型。診断時に腹膜播種を伴う場合が多い。
※8 PARP阻害剤:DNA修復に関わる酵素の一つであるPARPの働きをおさえる薬剤。卵巣がん細胞はDNA修復のしくみに異常がある場合が多く、そこでさらにPARP阻害剤によってDNA修復を妨げると、DNAの異常が蓄積し過ぎてがん細胞が生存できなくなる。
【関連リンク】
医学部 医学科 教授 松村謙臣(マツムラノリオミ)
https://www.kindai.ac.jp/meikan/2124-matsumura-noriomi.html