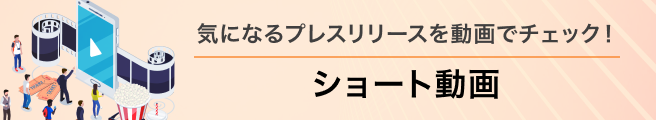低出生体重児への「手あて」に脳血流増を抑える効果 近畿大学医学部附属病院が検証・解明
出生時の体重不足から集中治療室で保育される「低出生体重児」に対し、採血など不快な刺激を与えるとき、新生児の全身を両手で包み込むことが、医療現場では長く行われてきました。この動作は「手あて(ホールディング)」と呼ばれ、児を落ち着かせたり安心させたりする効果があると言われてきましたが、「手あて」の効用に関する科学的な検証はなされてきませんでした。
このほど、近畿大学医学部附属病院リハビリテーション部(福田寛二部長)の本田憲胤・理学療法士が、この検証を試みました。その結果、痛覚刺激に対する生体反応として児の脳内で発生する血流の増加を、「手あて」が抑制していることを解明しました。
脳血流の増加が頻繁に起こることは、低出生体重児の脳の成長に影響を与え、脳容積の低下を招くリスクがあるだけでなく、発達障害との関連性も指摘されています。低出生体重児医療の現場で長年にわたって行われてきた「手あて」には、そうしたリスクを軽減する科学的な効用があったことになります。本田理学療法士は今回の検証結果について「これを契機に、低出生体重児に対する手あてが、NICUにおける標準的ケアとなることを期待しています」と話しています。
出生時の体重が2,500グラム未満の新生児は「低出生体重児」と呼ばれ、生命機能の未熟さに起因する合併症を避けるため、新生児特定集中治療室(NICU)で保育されるのが一般的です。しかしNICUは母胎内とは異なり、治療機器の騒音や採血による痛みなど、児にとって快適ではない環境であり、これが正常な発育・発達の阻害やさまざまな発達障害につながる可能性が指摘されてきました。
今回の実証実験は、睡眠中の低出生体重児10人に対し、ボールペンの先で1秒ほど軽く突く程度の軽微な痛覚刺激を踵(かかと)に与え、近赤外光脳計測装置(光トポグラフィ)を用いて脳血流の変化を測定しました。
その結果、脳内の前頭前野と感覚運動領域での血流が平常時の約10倍に増加しました。一方で、同じ刺激を与えながら「手あて」を施した児では、脳血流の増加が平常時の半分以下に抑制されていました。 「手あて」によって脳血流増加が抑制されるメカニズムについて、本田理学療法士は「痛覚とは異なる心地よい刺激が加わることで、痛みへの生体反応が緩和されているのだろう」と話しています。
日本ディベロップメンタルケア研究会会長である仁志田博司・東京女子医科大学名誉教授は、今回の研究成果について「急速な脳の発達期にある早産児はNICUという子宮内とは異なった環境にさらされています。児に対するタッチケアやスキンシップなどの働きかけ(良い刺激)は、脳機能・心にポジティブな作用をおよぼすといわれてきましたが、本研究はこの作用を初めて科学的に証明し、学問的価値の高い研究といえます」とのコメントを寄せています。
この研究内容は2012年7月22日発行の学会誌(電子版)「Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed」に掲載されました。
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed : 胎児・新生児医学分野で著名な英国雑誌